こんにちは。
白髪老師のサバ男です。
外国人に日本語を教えています。
TVで日本語を流暢に話す外国人タレントが増えてきました。
相当な努力をしたんでしょうね。
また、最近では一般の人でも日本語を話す外国人を多く見かけます。

日本人は日本語が難しいと思っています。
だからカタコトでも日本語が話せる外国人に会うと、「日本語お上手ですね!」とびっくりします。
たしかに、文字はひらがな・カタカナ・漢字と3種類あるし、敬語の使い方などは日本語母語者でも間違うことが少なくありません。
それでも、比較的短期間で日常会話まで話せるようになる外国人は多いです。
なぜ外国人が日本語をスムーズに話せるようになるのか。
その理由は日本語教育の方法にあると思います。
ここでは、日本語教育をどのように行っているかをお知らせしたいと思います。
日本語学校の初級クラスと中学校の英語の授業の時間はほぼ同じ
コロナ禍で来日する外国人は減ってしまいましたが、落ち着いたらまた多くの人が日本に来てくれることでしょう。
その中には留学や仕事などで日本語が必要になり、日本語を勉強する人も少なからずいます。
留学試験対策とか、ビジネスでの日本語表現を学ぶとか、外国人の日本語学習の動機は様々です。
高校時代に日本語を勉強したとか、アニメに興味をもって独学したとか、事前に日本語の知識がある人はいますがどちらかというと少数派。
「コンニチハ」「オハヨーゴザイマス」など、挨拶くらいしか知らない人の方が多い感じです。
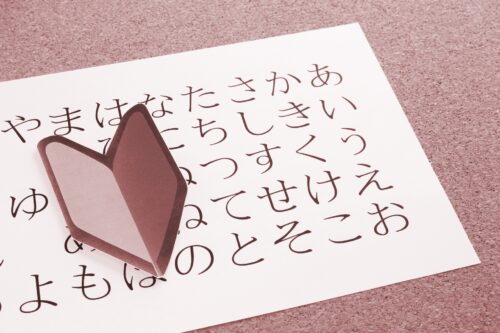
そんな彼らに日本語教育を行うのが日本語学校。
学校によってレッスン方針は違いますが、日本語教育の進め方は共通の雛形のようなものがあります。
入門レベルの人でも、初級テキストを学校のレッスンなら概ね300時間くらいで終了、自習を同じくらいするとして計600時間程度で日常会話はほぼ大丈夫なレベルに到達します。
CEFR(セファール)では初級者を卒業するA2レベルです。
日本の英語教育では中学校卒業レベルくらいでしょうか。
CEFRについては別の記事にまとめているので、よかったら読んでみてくださいね。
ちなみに、平成21年に定められた中学校学習指導要領では外国語の授業時間は各学年140時間で、3年間の合計になると420時間ですから、大体同じようなものでしょう。
中学校の授業時間は60分ではないですし、中間・期末などの定期試験もありますからね。
つまり、中学校の英語の授業時間と同じくらいで、日本語を学ぶ外国人は日本語の日常会話をマスターしていることになります。
日本語レッスンは日本語で教える直接法
「仕事は外国人に日本語を教える日本語教師です。」というと、少なからず「英語話せるんですか?」という反応が返ってきます。
中学校での英語の授業を思い出すのでしょう、学習者が理解できる言語で説明すると思っている人が実に多いです。
英語で日本語レッスンを進める学校はありますし、外国での日本語学校では現地の言葉で教えているところはありますが、全体的には少数派です。

学習対象の言語をその言語で教えるやり方を「直接法」といいます。
英語なら英語で、フランス語ならフランス語で教えるやり方です。
日本語レッスンは日本語で教える直接法を採用する日本語学校がほとんどです。
直接法の特徴をあげると、以下のようなものになります。
- 語彙や表現の意味は、実物・写真・絵・動作などで伝える。
- 文法や用法は例文で理解させる。
- 教師は学習者の母語で説明しない。
- 抽象的な意味の語彙は初級では教えず、中級以降に教える。
- 文字教育は会話よりも優先順位を下げる。
直接法は意味の説明が回りくどくなり、正確に伝わりにくい短所がありますが、学習する言語に接する機会が多く、その言語で考える習慣ができるという長所もあります。
日本語レッスンは導入→練習→定着の確認という流れで進みます。
「日本語わからないのに、日本語で説明してわかるの?」という声が聞こえてきそうですね。
もちろん、複雑な表現で説明してもわかりませんから、日本語レッスンには進め方というものがあります。
まずは、語彙や文型などの導入です。
えんぴつや腕時計などを見せて、「えんぴつ」「とけい」などと発音して、日本語でどう言うかを示します。

そのあと、覚えてもらった物を教師のすぐ近くに置いて、指を指しながら
「これはとけいです。」
といって文型を示し、どんな状況の時に使うかを理解してもらいます。
また、「これ」「それ」「あれ」を使う時は少し工夫が必要になります。
時計が話す人の近くなのか、聞く人の近くにあるかによって、「これ」か「それ」かが違ってきますから。
続いて、練習です。
練習方法はリピート練習や代入練習など、いくつかあります。
リピート練習は教師が言ったことをそのままリピートしてもらうもの。
代入練習は、別の言葉に置き換えていってもらうもの。
「時計」を「えんぴつ」「本」「新聞」などに変えて言ってもらう練習です。
あとは、疑問文や回答文なども同様に導入→練習を繰り返していきます。
最後に定着の確認です。
レッスン中に覚えてもらった文型を使って、会話練習をすることが多いです。
「これは新聞ですか?」「いいえ、それは本です。」
「あれは時計ですか?」「はい、あれは時計です。」
といったような感じでお互い話してもらいます。
正しい質問文が言えるか、質問文を理解して正しい回答文が言えるか、その回答文が質問に合っているか、こういったことをお互いに確認します。
日本語レッスンは基本的にこういった内容で学習項目の繰り返し。
レッスンが進むと説明に使える表現も増えていきますが、既習の語彙や表現だけで説明していきます。
もちろんどこかのタイミングで五十音とともに、ひらがな・カタカナなどの文字も教えます。
それでも全体的な進め方は会話が中心。
これを進めていくうちに、日本語の会話力もどんどんついていくわけです。
まとめ
自分の意志で日本に来て日本語を学ぶ外国の人は、それなりに国際的な感覚をもっています。
英語母語でない人は、英語を含む複数言語が話せる人も少なくありません。
ある意味、外国語を勉強するのに慣れている人たちです。
そういう背景もあるかもしれませんが、中学3年間の英語の授業時間と同等の時間で日本語の日常会話が可能になるのは、素直にすごいと思います。
日本語を勉強しているのは欧米の人たちよりも、中国や韓国をはじめアジアの人々が多いです。
日本語学校の教室は、まさに世界の縮図。
言葉も習慣も異なる学習者の人たちが同じように日本語をマスターしていけるのは、日本語教育の普遍性を示していると思います。
導入→練習→定着の確認
このサイクルは外国語を学習するときの一つのパターンになります。
日本人が外国語を学ぶ時にも大いに参考になると思います。
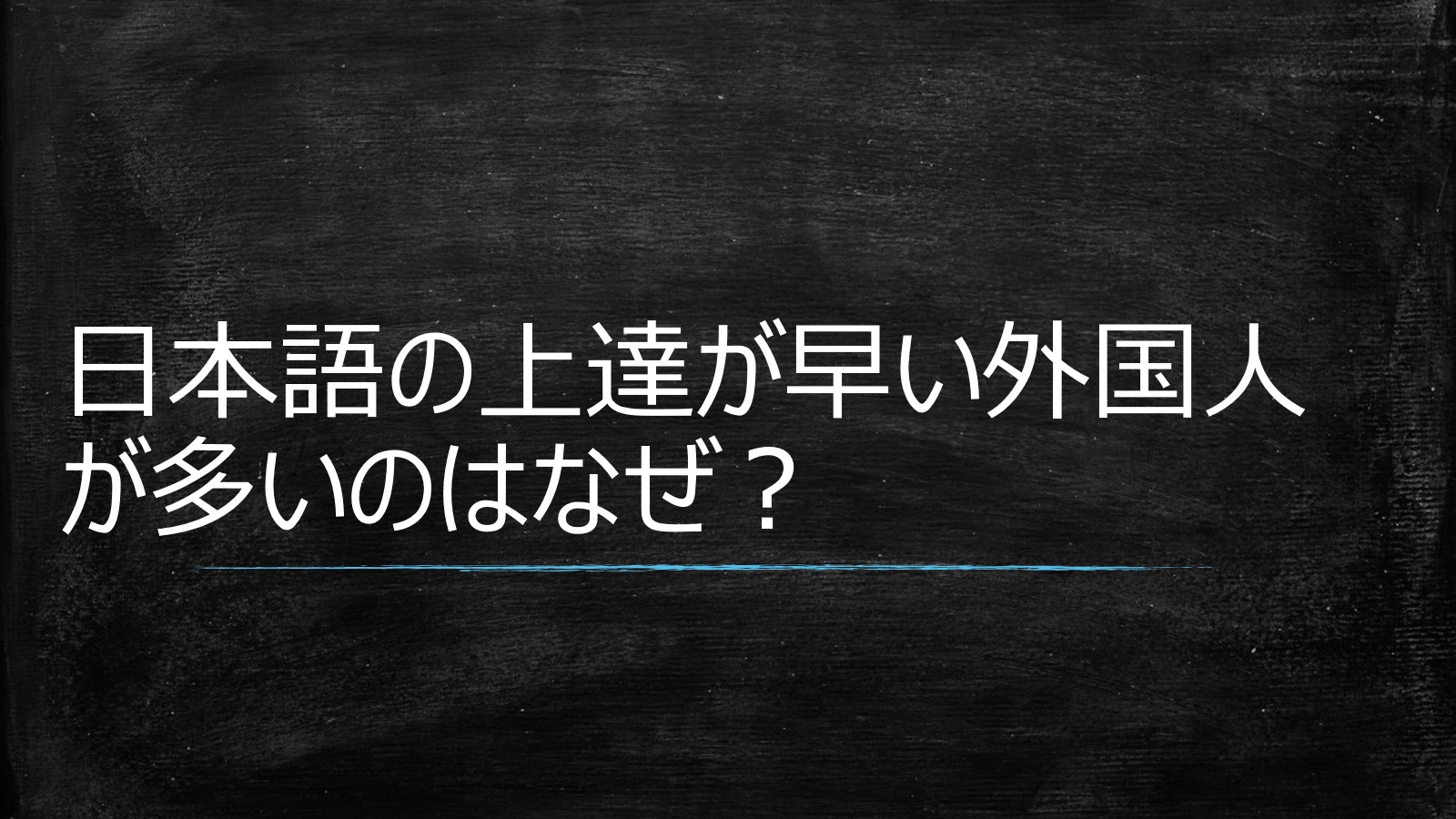
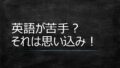
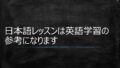
コメント